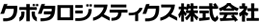「困ったときはお互い様。自分にできること。」~第一章~
2月1日の能登半島で感じた支援の意味


2024年1月1日に発生した能登半島地震から、1年以上が経ちました。現在、復興の2年目を迎えています。しかし、現地に行ってみると、まだまだ復興の道のりは長く、支援が必要な状況が続いていることを実感しました。
今回、支援活動の一環として能登・輪島を訪れ、現地の方々と交流し、スポーツを通じて笑顔を届けよう。
ということで行ってきました。
僕はアスリートの社会貢献チームのHEROsの一員として、参加しました。
https://sportsmanship-heros.jp/
この体験を通して、感じたこと、気づいたこと、そして「支援とは何か?」ということを考えさせられましたので、少し綴っていきたいと思います。
壊れた街と、進んでいく日常
金沢駅に着いたとき、街の様子は普段と変わりません。ただ、バスで輪島へ向かい車を走らせると、目の前に広がる景色がどんどん変わっていきます。
壊れた家、家の中に入り込んだ土砂、1月1日のまま時間が止まったような場所…。
地震が起きてから6回目の能登。
いつも思う「復興はまだまだやな。」と。
輪島の方に来るとそんな光景が広がっています。
でも、その一方で仮設住宅や支援の拠点もあり、復興に向けて動いている人たちの姿も見えました。
特に印象に残ったのは、壊れた家の前を子どもたちが歩いている光景でした。
建物は壊れたまま。でも、日常は止まらずに進んでいく。
復興のスピードと、そこで暮らす人たちの時間の流れの違いを強く感じました。
「忘れてはいけないけど、忘れてしまうこと」
「忘れたいけど、忘れられないこと」
困ったときはお互い様。みんなで支え合っていくことは忘れてはいけない。

関連死が地震の直接死を上回るという現実
今回、現地を訪れて改めて深刻だと感じたのは、地震の直接的な犠牲者を上回る数の関連死が発生しているということです。(現在の関連死は307人 2月14日現在)
災害によって住環境が変わり、避難生活が続くことで、健康を崩して命を落とす方が増えている。これは、今後も続く可能性が高いです。
つまり、「地震の被害は終わった」のではなく、いまも続いているんです。
この関連死の問題を少しでも食い止めるためには、
僕たち一人一人が「今、何ができるのか?」を考えて行動することが必要だと強く思います。
「失っていい命などないはずです。」

〈次回に続く〉
※災害関連死とは
地震や津波などの直接的な被害による死亡ではなく、避難所生活での過度のストレスや環境変化、医療体制の不備などによって引き起こされる死亡のこと